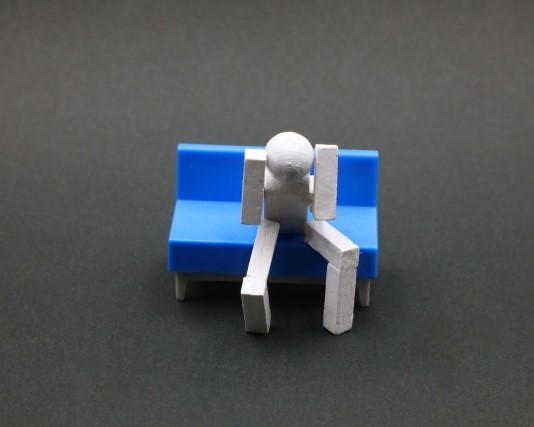こんにちわ。
リキュアの堀ノ江です。
今回は片頭痛についての最近有力とされている仮説についてお話していきます。
片頭痛の特徴としては片側または両側に出現する頭痛で、脈うつような強い痛みです。
随伴症状として吐き気、嘔吐、光・音に過敏になり、前兆として視覚性の症状が多く見られます。
片頭痛に関しての明確なメカニズムは現状解明しきれていません。
いくつもの仮説がある中で最有力な仮説に三叉神経血管説というものがあります。
今までの有力仮説~血管説~
血管説とは
①前兆で脳血管収縮により脳虚血状態になる
②収縮した血管が異常に拡張する
③血管に分布する痛覚感受性神経が刺激され事で片頭痛発作が起こる
というものでした。
これらは片頭痛が脈うつ痛み(拍動性)であること、片頭痛が側頭部の動脈(浅側頭動脈)の拍動に一致したことから提唱されました。
しかし、脳血流を観察した研究で脳血流の増加は見られたが、そのタイミングと痛みのタイミングが明らかにズレていた為、説明が出来ないとされた。
現在の有力仮説~三叉神経血管説~
三叉神経血管説とは
①三叉神経終末が‘‘何らかの刺激‘‘を受ける
②三叉神経終末から神経ペプチド(CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)、サブスタンPなど)を放出
③⁻A 血管透過性亢進が起こり、局所的な神経原性炎症が発生し頭痛発作を生じる
③⁻B 血管透過性亢進による影響で、軸索反射(隣接した神経でも③⁻Aが起こる)が起こり末梢神経感作が生じる
④③⁻Bにより、普段は問題ない刺激(血管の拍動など)でも痛みを感じてしまう
この説の中で重要なのが②で放出されるCGRPという神経ペプチドです。
CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)
CGRPは体内で生成されるペプチド(アミノ酸が2個以上結合したもの)で血管拡張や炎症反応に関与する物質です。
片頭痛においてCGRPの役割で最も重要なのが、「感作誘導」です。
感作とは刺激に対して過剰に反応してしまう事で、その反応を誘導する役割があるという事です。
メカニズムとしては
①三叉神経終末(無髄C繊維)からCGRPが放出される
②隣接する三叉神経終末(有髄Aδ繊維)のCGRP受容体が①で放出されたCGRPと結合し、中枢神経に痛みシグナルを伝達
これらにより痛みが拡散し、通常は痛みを感じない血管拍動や脳圧の変化が痛みとして感知されてしまうのが片頭痛ではないかと考えられています。
そのため最近の薬物療法ではCGRPに対してのお薬が2021年から使われ始めています。
リキュアでのサポート
当院で行っている背骨調整では治療と予防が可能です。
治療では頚椎2・3番を調整する事で痛みをとる事が可能です。
これらを調整する事で脳への血流、神経伝達を改善します。
血液は栄養を運んでくれる手段で、血流が悪くなると栄養不足により緊張が増し頭痛発作に繋がります。
そのため頚椎2・3番の調整は改善効果があるのです。
また三叉神経支配である筋肉とのつながりもあり、筋肉の緊張を緩める事で頭痛の改善も可能です。
片頭痛でお悩みの方、近くで片頭痛に困っている方いらっしゃいましたら、是非リキュアをご利用下さい。
お待ちしております。
ご相談はリキュア銀座院・横浜中山院まで

ご予約はこちら⇓